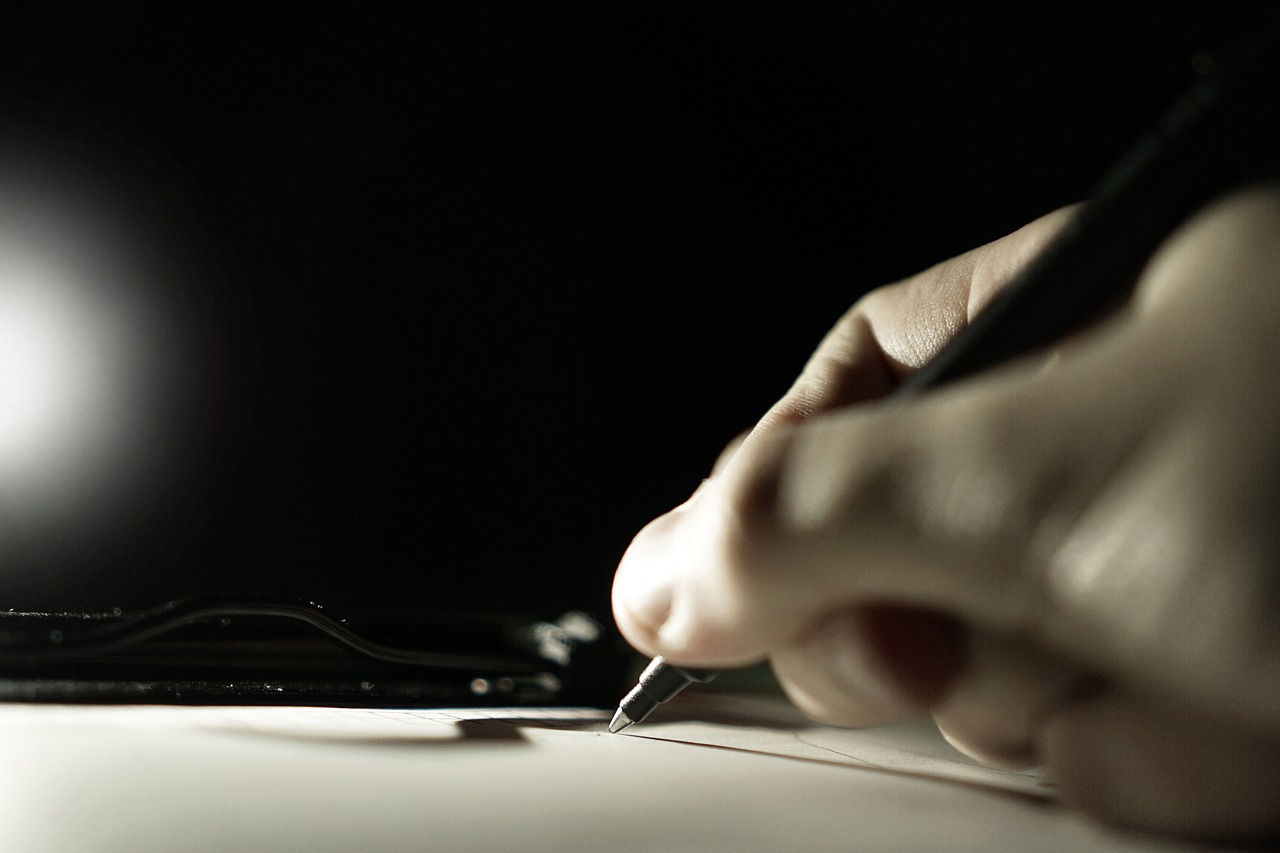ブログ
-
*生前整理その1
早いもので12月・・・師走ですね。
皆さんは大掃除に取り掛かっていますか?
今回は生前整理のお話です。
『生前整理』とは、いざという時に必要なものがすぐに準備できるようにしておくことです。
年齢を重ねて増えたモノの整理を行い、家の中の動線を確保したり転倒でのケガを防ぐという目的もあります。
ちなみに『遺品整理』とは、亡くなった方が所有していた動産物全般の整理を指します。
一般的には四十九日法要を終えてからと言われていますが、「ご遺族の気持ちの整理がついたら」、「親族が遠方で何度も通えない」など、事情に合わせて行いましょう。
生前整理で不用品の処分が体力的に難しい場合は、子どもを巻き込んで手伝ってもらいましょう。
この機会を利用して、思い出話や財産のことまで想いも伝えることができます。
一気に片付けができない場合は、段ボールなどの箱に「大切」「処分」「保留」など大きく書いておくことで後々整理しやすくなります。
-
*11月30日は『人生会議の日』
将来の変化に備え、医療及びケアについて本人を主体に、そのご家族や近しい人、医療・ケアチームが繰り返し話し合いを行い、本人による意思決定を支援する取り組みのことを『ACD(アドバンス・ケア・プランニング)』といいます。
これは厚生労働省も推奨していることで、『人生会議』とも呼ばれています。
終活とは、人生の終わりに向けて最後まで自分らしくいられるために、元気なうちに前向きに、自分が死ぬまでのことと死んだあとのことを具体的に考え、希望を伝え、準備することです。
早め早めに取り組み、身体も頭も元気なときに希望する医療や介護について家族や身近な人と話し合っておくことはとても重要なことです。
-
*夫婦について考える
この時期になると、テレビや週刊誌で”理想の芸能人夫婦”が発表されていますよね。
11月22日が『いい夫婦の日』だというのは、財団法人余暇開発センター(現 財団法人生産性本部)により1988年に制定されたそうです。
この日に入籍(婚姻届提出)される方も多いのではないでしょうか。
ちなみに『よい夫婦の日』というのもあり、こちらは4月22日の語呂合わせからきているそうです。
さて、私も気付けば結婚生活が20年以上になりますが、割と平和に楽しくここまでやってこれました。
夫と親には感謝しかありません。
そりゃあね、たまには険悪ムードの時もありますよ。
仕事で嫌なことがあった時、単に虫の居所が悪かった時など。
そんな時は必要以上に近づき過ぎず、適度な距離感を保つようにしています。
言い合いになっても、根底に相手を思いやる気持ちがあれば夫婦関係だけでなく、友達との友情関係なんかも些細なことで崩れてしまうことはないと私は思っています。
とはいえ、ツーカーの仲になった夫婦でも、心の中の真意までは分かりません。
終活では、自分の思いや希望(意思表示)を伝えることが大切です。
エンディングノートに書いたなら、そのことを家族や周りの人に伝えておいて下さい。
パートナーだけでなく、友人や、もしかしたらこの先お世話になるかも知れない医療者や介護者にも自分の気持ちは言葉にしないと伝わりません。
周りの人には感謝の気持ちを忘れずに接していくことで、自分の幸せな結末(最期)に結びつくのではないでしょうか。
ご縁があって一緒になった結婚相手。
これからも楽しく夫婦をやっていこうじゃないの。
-
*おひとりさまの終活
人間誰しも死ぬ時は一人といいますが、亡くなる前後に面倒をみてくれる人がいるかどうかは大切です。
自分の希望や思いをエンディングノートに書いていたとしても、それを実行してくれる人がいなければ、それらを叶えることはできません。
「おひとりさまの終活」は誰に託すのかが重要なポイントになります。
パートナーや子どもがいない場合、身内だと甥や姪に頼ることになると思います。
また、地域の世話人や友人・知人になるかも知れません。
どちらにしろ、日頃から万一の際にお願いすることを伝えておきましょう。
自分より若い世代の身内や友人とコミュニケーションをとっておくことも必要です。
人間関係は1日にしてできるものではありません。
日々のお付き合いの中で築き上げていくものです。
近所の集まりやボランティアなど、健康で動けるうちは積極的に参加しましょう。
-
*11月8日は『いい歯の日』
歯の健康を保ち、長持ちさせるには、かかりつけ医による定期検診やクリーニングと自分に合う歯ブラシで適切な歯のセルフケアを両輪で行うのがカギだそうだ。
日本人の約8割が1日に2回以上、歯磨きをしているというが、虫歯ゼロの人は少なく、加齢とともに歯周病に悩む人は多い。
丁寧に磨いているつもりでも、汚れを落としきれていないことがあるので、やはり定期的に歯科に通うことが大切だと思う。
ここで問題。
「歯磨き粉は少しだけつけるorたっぷりつける」
どちらが正しいのか?
以前はあまり泡を立てると磨きにくく、磨き残しが増えるため、少ない歯磨き粉で磨くことが推奨されていた時期もあった。
私もその時の記憶があり、歯磨き粉は少なめがいいと思っていた。
しかし現在は1000〜1450ppmの高濃度フッ素入り歯磨き粉をブラシ部分の3分の2以上につけることが推奨されている。
時代の変化とともに、昔は推奨されていたことが検証の結果違っていたということもある。
“おばあちゃんの知恵袋”的なもので”やけどにはアロエ”と言われていた時代もあったが、アレルギーを引き起こし、塗った場所にかぶれが出るかも知れないことから、今はまず冷やすことが推奨されている。
歯磨きの方法だけでなく、物事はどんどん進化しているので私たちもアップデートをしなければならない。
今回『歯』について書いたのは、歯周病と認知症には関係があるからだ。
歯を喪失し、入れ歯を入れずにそのまま放置している人は、20本以上歯が残っている人と比べて認知症の発症リスクが約2倍高くなるという報告も出ている。
噛む力の低下や栄養の偏りなどが起こり、認知機能が低下すると考えられている。
歯周病菌による悪影響は認知症だけでなく、糖尿病や心筋梗塞、脳卒中など、寿命を縮めるようなさまざまな病気に関わっている。
アルツハイマー病の原因と見られるアミロイドβの蓄積は40代後半からすでに始まっている。
糖尿病や動脈硬化も中年以降、一気にリスクが高まる。
つまりこの時期からしっかりと歯周病菌をコントロールしていれば、さまざまな病気の進行を未然に食い止められる可能性が高いと言えるのだ。
セルフケアだけでは未完全な部分を歯科に通うことで認知症をはじめ、さまざまな病気のリスクを少しでも減らすことができればと思い、私は来月の定期検診の予約の電話をした。
-
*明日オープンです
2024年11月2日 ROLLの喫茶コーナーがオープンします。
先だって関係者様にプレオープンのお披露目をさせていただいたのですが、お祝いの品やお花を頂戴し、皆様のお心遣い、本当に嬉しかったです。
と同時に、これから頑張っていかなければ・・・と気持ちが引き締まる思いでした。
人とのご縁を大切に、これからどんな出会いがあるか楽しみです
-
*オープン日 決定!
ROLLのオープン日が決まりました!
2024年11月2日(土)です。
ここ数日は開店に向けて内装工事の追い込みや関係者様との打ち合わせなどで、本当にバタバタしていました。
工事関係者様はもちろん、家族にも協力をしてもらい感謝の気持ちでいっぱいです。
私のこだわりやワガママにもお付き合いいただき迷惑もたくさんかけたと思いますが、素敵な方々に恵まれてここまで来ることができました。
本当にありがとうございます。
以前にも書きましたが、ROLLは気軽に終活に触れてもらうことができるよう喫茶スペースを設けていますので、まずは喫茶店に行くような感覚でお越しいただければと思います。
その上で終活に興味があるけどなかなか踏み出せない方や、何から始めたらいいのか迷っている方のお手伝いができればと、考えています。
[個別相談] 11時〜18時(要予約)
[喫茶コーナー] 9時〜12時(土・日のみ営業)
-
*エイッ!と踏み出す勇気
面倒なことはついつい後回しにしてしまう・・・
で、直前になって慌てる。
私の悪い部分です(笑)
終活もそうですが、「そのうちエンディングノートを書こう」と思っていてもズルズル先延ばしになってしまっている方もいるのではないでしょうか。
終活でなくとも、やり残したことはないですか?
行ってみたいと思っていた場所への旅行や、キャリアアップのための習い事など。
前にも書きましたが、死を目の前にして多くの人が思うのは「やりたいと思うことをやればよかった」という後悔だそうです。
時間やお金、年齢を言い訳に後回しにしていると後悔が残る最期になってしまうかも知れません。
『気なったことはとりあえずやってみる』
新しく何かを始めたり自分の知らない世界に飛び込むには勇気が必要です。
私も起業したはいいけど、この先どうなるか分かりません。
でも、時間は有限です。
だからこそ人は頑張れるのではないでしょうか。
終活を通して自分の人生と向き合ったとき、新たな何かを見つけることができるかも知れません。
若い頃に描いていた夢を思い出すのもいいですね。
-
*残された者へのメッセージ
終活をする中で、遺言書を残しておくべきか悩まれている方も多いと思います。
エンディングノートに介護や医療について自分の望むことを書いておくのも大切ですが、遺産分割に関することなどは遺言書の方がいいでしょう。
前にも書きましたが、エンディングノートに法的効力はありません。
残された家族に対する想いは伝わると思いますが、強制力はないのです。
遺言があった方が望ましいケースとして、いくつか例を書いておきます。
まず、相続人同士で遺産分割協議をするのが難しいとき。
子がなく、たくさんの兄弟がいるが配偶者に話し合いをさせるのが大変そうだったり、付き合いのない甥姪が何人もいるようだが連絡を取るのが難しい場合、また、障がいをもった子に多く遺してあげたい場合などです。
それから相続人ではない者に遺産を分けたいとき。
相続人が一人もいないからお世話になった方や施設に遺したい、その他に、動物愛護団体やユニセフなど社会のために寄付したいと考えている場合や、お世話をしてくれた長男の嫁にお礼の気持ちとして遺産を渡したい、内縁関係(事実婚)のパートナーに遺したいと考えている場合です。
遺言で決定できるのは「遺産に関すること」と「相続人に関すること」です。
財産は天国に持っていけません。
自分が生きた証でもある財産を誰に、どのように分けるのか考えておきましょう。
-
*活用しませんか?成年後見制度
”夫の認知症が進み、正常な判断ができなくなった。
夫の土地を売って、介護費用に当てたい。売却の手続きは妻がする”
”父の認知症が進み、正常な判断ができなくなった。
父の定期預金を解約したいので、銀行の手続きは息子がする”
この2パターンですが、両方×です。
契約については家族であっても他人と同じなので本人の代理はできません。
認知症以外にも事故や病気などで判断能力が不十分になった人、知的障がい者や精神障がい者の権利や財産を守り意思決定を支援するのが『成年後見制度』です。
後見制度には「法定後見」と「任意後見」があり、判断能力が低下した時のためにあらかじめ準備しておけるのが「任意後見」です。
法定後見は家庭裁判所で選任されますが、任意後見は自分で後見人を選任して契約できます。
”今はまだ元気だけど、判断能力が低下してからの支援が欲しい”といった将来型や、”既に今困っているから判断能力が低下する前からの支援が欲しい”というふうな移行型など、本人の希望に合わせた段階でのプランも選べます。
任意後見契約にプラスして「見守り契約」や「死後事務委任契約」を一緒に締結することで、この先も安心して暮らせるのではないでしょうか。