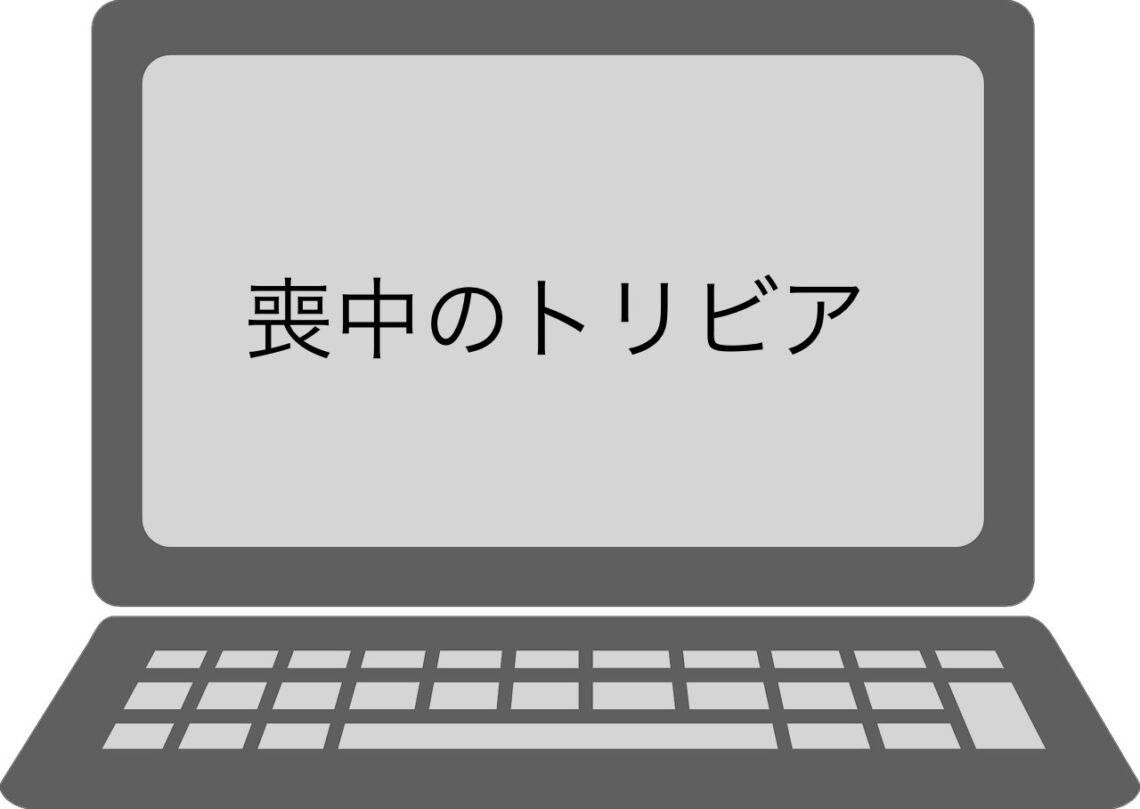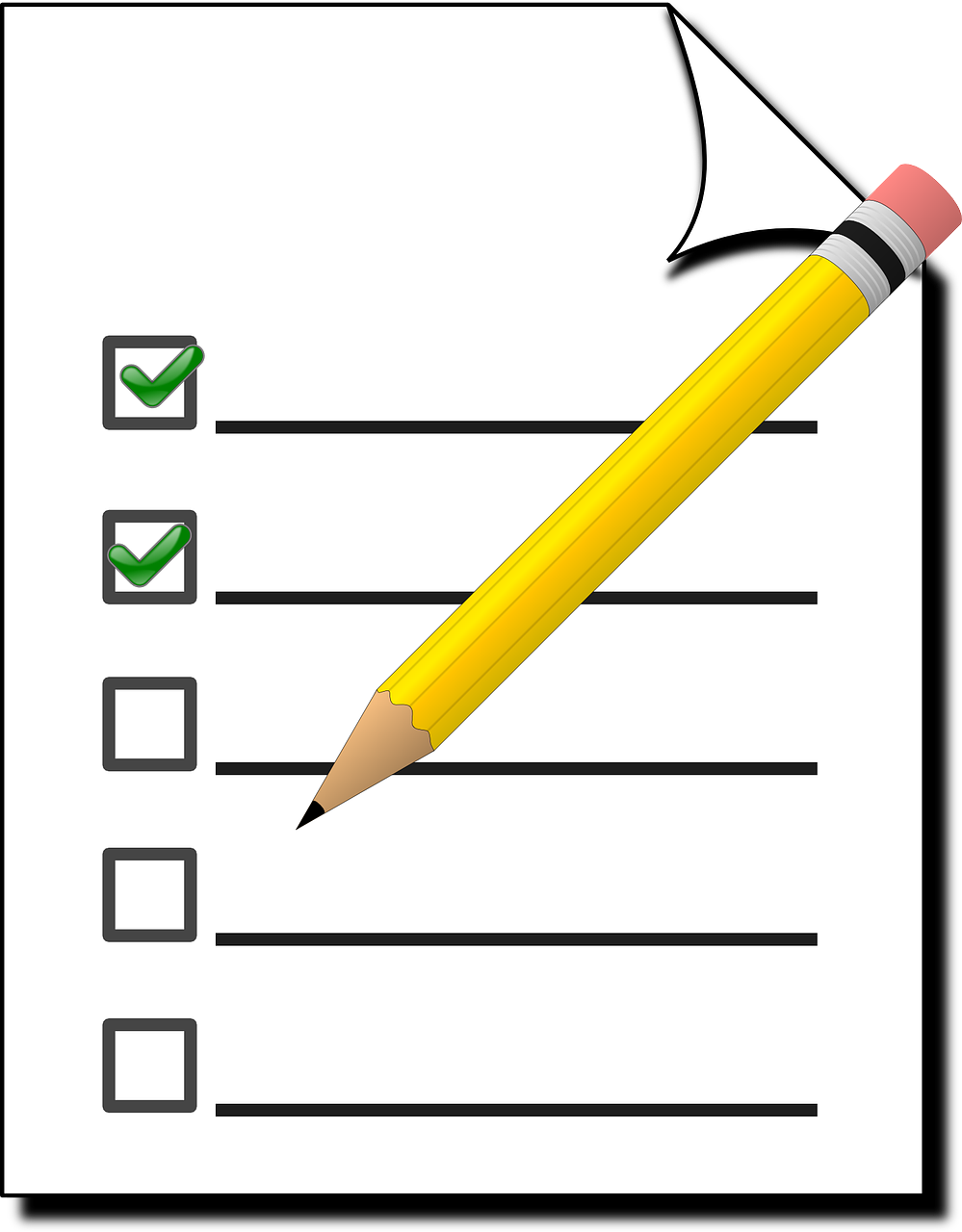-
*喪中にしてはいけないこと
お正月も過ぎ、いつもの生活が始まりましたね。
我が家は昨年祖父が亡くなり喪中なので例年とは少し違う年末年始になりました。
喪中の場合、年末の行事だと「年賀状は送らない」ということぐらいは知っていましたが、喪中の期間にしてはいけないことなど改めて調べてみると他にも色々ありました。
まず、神社への参拝は控えるということ。
神道では「人の死=穢れ」と考えられているため、神聖な神社に穢れを持ち込んではいけないという理由からだそうです。
私は毎年決まった神社へ初詣に行っていたのですが、今年はお寺に参拝に行きました。
仏教ではそういった考えがないことから、喪中の初詣やお墓参りなどお寺だったら問題ないみたいです。
他にも「慶事への参加は控える」「新年のお祝いを控える」など、祝い事を自粛するのが良しとされています。
新年の挨拶も「おめでとう」を使わなかったり、正月飾りやおせち料理の準備などの派手なことをしないことで故人を悼み慎ましく過ごすことに繋がるのだと思います。
年末年始の行事以外にも喪中の間は「大きな買い物をしない(家を建てたり)」とか「結婚式や入籍など新たな門出を祝う」ことは控えた方がいいみたいですね。
とは言え、何もかも制限してしまうのではなく、故人を想いながら自分らしく普段に近い生活をしていれば特に問題はないかと思います。
私はいつもと少し違った年末年始になりましたが、皆さんはどのように過ごされましたか?
-
*慌てないために
この時期になると雑誌の記事で『年末の大掃除特集!』なるものをよく見かけます。
そしてそれらを目にする度に憂鬱になります。
「もうそんな季節か…」
皆さんは年末の大掃除計画は立てていますか?
到底一日では終わらない家中の掃除。
今日はキッチン、明日はお風呂場、と何日かに分けてすることになりますよね。
そもそも普段から気付いた時にこまめにやっておけば、わざわざ忙しい年末に大掃除しなくてもいいんだけど…。
毎年思います。
そうなんですよ、いきなり年末はやって来ません。
「分かっちゃいるけど…」
面倒なことはついつい後回しにして後悔する訳です。
「もう少し早めに取り組んでたら良かったな…」
私も面倒だと思うことは後回しにするタイプなので偉そうなことは言えませんが、最近は後悔を減らすためにも早め早めの行動を心がけています。
終活も同じです。
大切な人が亡くなってからでは遅いのです。
意思表示ができなくなってからでは遅いのです。
自分のため、そして残される者のためにも想いや希望はエンディングノートなどに書いておきましょう。
そろそろ12月、新しい年を気分よく迎えるためにも今年やり残したことは片付けてしまいましょう。
-
*続・夫婦について考える
明日は11月22日『いい夫婦の日』ですね。
去年の今頃も夫婦についてブログを書いた記憶がありますが、一年というのは本当に早いです。
これは年齢を重ねるにつれ、ますます早く感じるようになった気がします。
最近些細なことで夫と少し喧嘩気味になったので、改めて夫婦について考えてみました。
皆さんは「男性脳」「女性脳」という言葉を聞いたことはありますか?
特徴としては、結果重視な男性脳に対し、プロセス重視の女性脳。
会話ひとつとっても解決策を求める男性脳と、共感を求める女性脳では目的がずいぶん違ってきます。
脳全体の構造に性差はないとされていますが、これらは遥か昔、狩猟をしていた頃、獲物を捕え家族に食べさせることを一番に考えていた男性は目的達成を重視し、ひとつのことに特化して取り組む傾向があるとされています。
一方女性は集落内で協力し合って子育てをする中で、周りとの共感や共有が重要視されてきました。
こうしたことから子育てや家事を並行してできる能力が発達し、周りの変化などを敏感に察知する能力も長けているのです。
しかし近年の研究では、「男性脳」「女性脳」という単純な二元論では説明できないとも言われています。
確かに、多様性が謳われるこの時代に「男性だから」「女性だから」というのは少し遅れていると思います。
男性でも女性的な特徴や考え方が見られることもあるし、またその逆も然り。
男性の方が家事が得意な夫婦もいるだろうし、女性に家のことを全て任せてしまう時代は終わろうとしています。
とは言え、私の年代では昔の名残か、奥さんが働いていても子育てや家事の比重は女性の方に重くのしかかっているのが現実です。
そして夫婦で長年連れ添っていると「ありがとう」や「ごめんね」の言葉が少なくなってきていると思います。
多分、他人に対してなら”してくれて当たり前”とか”言わなくても分かってくれるだろう”とは考えないでしょう。
そもそも夫婦も元は赤の他人。
そんな二人がうまくやっていくためには、相手のことを思いやり、感謝や謝罪をきちんと口にすることが大切だと改めて思いました。
終活もそうです。
自分の希望や思いは言葉にしないと周りには伝わりません。
こちらがいいと思ってしていることも、相手にしてみれば迷惑なことかも知れません。
11月30日は『人生会議の日』です。
この機会にこれからのことについて、パートナーや家族と話し合ってみませんか?
-
*秋の過ごし方
たまに昼間は暑さを感じる日もありますが、朝晩は肌寒い季節になりましたね。
やっと秋の到来です。
秋といえば『食欲の秋』『スポーツの秋』『芸術の秋』・・・と色々ありますが、皆さんは秋にどんなイメージをお持ちでしょうか。
秋刀魚や栗、松茸など秋の味覚はたくさんあります。
夏に食欲が落ちていた人は『食欲の秋』を楽しむのもいいですね。
最近ではハロウィン(10月31日)も秋の行事として定着してきたように思います。
日本では仮装した多くの人が集まるスクランブル交差点にDJポリスが出動する娯楽性の強いイメージですが、起源は古代ケルト文化の「サウィン祭」だそうです。
この日は死者の霊が家族に会いに戻ってくる日とされており、その時ご先祖様の霊だけでなく、悪霊や悪魔も一緒にやってくると考えられていました。
その悪霊や悪魔を追い払うため、自分を仲間と思い込ませるために恐ろしい姿(仮装)をしていたのだとか。
そう考えると日本のハロウィンはパーティー感覚で、宗教的な意味合いは気にされていないように感じます。(笑)
さて、私の秋は『読書の秋』でしょうか。
秋だからという訳ではないのですが、私は時間ができたら近所の図書館に行くことがあります。
仕事関係の本を借りるときもあるのですが、最近のお気に入りは絵本コーナーです。
先日は時期的にオススメされていたハロウィンのお話の絵本を読みました。
あと、ヨシタケシンスケさんの絵本もよく手に取ります。
子どもの頃の純真無垢な心で読んでいたあの頃と、大人になってさまざまな方向から内容を汲み取れるようになった今では楽しみ方も違い、絵本は奥深いなあと思います。
難しい本でなくとも、心を豊かにしてくれる絵本を読みに図書館に足を運ぶのが私の秋の過ごし方です。
-
*終活を考える
秋の気配を感じられるようになったと思えばもう10月。
今年の夏は本当に暑かったですね。
やっと過ごしやすい季節になったと安心していたらすぐに真冬になりそうでこわいですが・・・。
さて、10月1日は『終活を考える日』でした。
終活という言葉は割と浸透してきていると思いますが、実際に行動に移している人は少ないのが現状です。
「何から始めたらいいのか分からない」
「誰に相談したらいいのか迷う」
こういう理由で終活が始められない人が多いのでないでしょうか。
いきなり弁護士さんの所に行くのは敷居が高いと思います。
そんな方々のお話をじっくり聞かせていただき、寄り添いながら終活を具体的に進めていくサポートをするのが私の仕事です。
終活を始めるタイミングに決まった年齢はありません。
人生の節目(定年退職、還暦、古希など)であったり、病気の告知や余命宣告を受けたとき、子や孫から終活を勧められたときなど人それぞれですが、終活を成功させるポイントは以下になります。
①身体も頭も元気なうちに始める
②節目のタイミングを利用して万一の時に備える
③「終活を始めたい」と思った時に始める
早め早めに取り組み、”後悔しない”エンディングプランを組み立てて行くことが成功の秘訣です。
-
*防災月間
9月も終わりに近付き、最近やっと涼しさを感じられるようになった今日この頃。
こういう季節の変わり目は体調を崩しやすいので、夏の疲れがたまっている方は生活習慣の見直しをしてみるのもいいですね。
さて、9月は防災月間でした。(9月1日は防災の日)
皆様は災害に対する備えはしていますか?
以前のブログでも書きましたが、防災と終活は似ている部分があると思います。(ブログ「防災と終活」)
”準備しておいた方がいいのは分かっているけど何から始めたらいいのか分からない”
”まだ先のことだから、そのうちでいいかな”
こんな感じで腰が重い人はたくさんいると思います。
いつ来るか分からないことに対して準備するのは難しいですよね。
しかし、『もしものとき』が来てしまってからでは遅いこともあるのです。
重要なことだけど緊急性がないことから、実際に行動に移す人が少ないという点でも防災と終活は似ているのではないでしょうか。
では実際に防災グッズで何を用意すればいいのか。
非常用持ち出し袋(避難の際に持ち出すもの!)
・水 ・食品(ご飯、レトルト食品、ビスケット、チョコ、乾パンなど最低3日分) ・防災用ヘルメット、防災用ずきん ・衣類、下着 ・レインウエア ・紐なしのズック靴 ・懐中電灯(手動充電式が便利) ・携帯ラジオ(手動充電式が便利) ・予備電池、携帯充電器 ・マッチ、ろうそく ・救急用品(絆創膏、包帯、消毒液、常備薬など) ・使い捨てカイロ ・ブランケット ・軍手 ・洗面用具 ・歯ブラシ、歯磨き粉 ・タオル ・ペン、ノート ・マスク ・手指消毒用アルコール ・石鹸、ハンドソープ ・ウエットティッシュ ・体温計 ・貴重品(通帳、現金、パスポート、運転免許証、病院の診察券、マイナンバーカードなど)
子供がいる家庭の備え
・ミルク(キューブタイプ) ・使い捨て哺乳瓶 ・離乳食 ・携帯カトラリー ・子供用紙オムツ ・お尻ふき ・携帯用お尻洗浄機 ・ネックライト ・抱っこひも ・子供の靴
女性の備え
・生理用品 ・おりものシート ・サニタリーショーツ ・中身の見えないごみ袋 ・防犯ブザー、ホイッスル
高齢者がいる家庭の備え
・大人用紙パンツ ・杖 ・補聴器 ・介護食 ・入れ歯、洗浄剤 ・吸水パッド ・デリケートゾーンの洗浄剤 ・持病の薬 ・お薬手帳のコピー
その他にも、備蓄品(お家に備えておくもの)として、
・食料や水(最低3日分、できれば1週間分×家族分)
・生活用品(ティッシュ、トイレットペーパー、ラップ、ごみ袋、ポリタンク、携帯用トイレ・・・など)
[出典:とくしん+1防災編 災害の「備え」チェックリストより]
防災の準備も終活も一度にやり切ろうとすると疲れてしまいます。
家族と話し合いながら進めてみてはいかがでしょうか。
『備えあれば憂いなし』
いつかは必ず訪れる「もしものとき」に備えて今できることはしておきましょう。
-
*計画と実行の日
皆さんは「PDCAサイクル」をご存知ですか?
ビジネスシーンではよく聞く言葉ですが、私は恥ずかしながら起業するまで知りませんでした。
Plan(計画)Do(実行)Check(評価)Action(改善)の4つを繰り返し行うことで業務の質や効率を継続的に改善する方法です。
9月5日は『計画と実行の日』とされているのですが、これは計画を立てて実行することの大切さを世の中に広めていくことを呼びかけています。
PDCAサイクルはビジネスシーンだけでなく、日常でも使えると思います。
例えばダイエット。
まずは目標のゴールを決め、そのためには何をしたら良いのかPlan(計画)を立てます。
次は立てた計画に沿って実際に行動に移すDo(実行)。
運動を取り入れるとか食事を見直すとか。
成果は出ているか、目標は達成できたか、実行した結果を振り返るのがCheck(評価)になります。
その結果を基にうまくいかなかった点は見直し、効果的だった方法は継続するのがAction(改善)です。
ビジネスシーンはもちろんですが、普段の生活でも「PDCAサイクル」を活用することによって自分の生活習慣などを改善することもできそうですね。
-
*残暑お見舞い申し上げます
気付けば8月も中旬、お盆ですね。
”徳島の夏”といえば、やはり阿波おどりでしょうか。
私は14日に行って来ました。
期間中、毎年1回は観に行くのですが、今年は例年より外国の方が多かったような気がします。
浴衣を着ていたり、コスプレっぽい服を着ていたりと、日本を楽しんでいる様子でした。
先週祖父が亡くなり、ここ数日は死後の事務手続きなどで忙しかったのですが、「今日はゆっくり休む」と決めて阿波おどりを楽しんで来ました。
お盆といえど、もちろん仕事の方もいるでしょうし、お子さんが夏休みだったりする親御さんは毎日の食事や遊びに連れて行ったりでお疲れのことでしょう。
時間がある時は、ぜひ自分を癒してあげてください。
ゆっくりお風呂に浸かったり、好きな漫画に没頭したり、休日はダラダラ過ごしたり、たまには自分を甘やかしてあげてはいかがでしょうか。
そうすることで、また明日からの活力になるはずです。
まだまだ残暑が厳しいですが、皆様もお身体ご自愛くださいね。
-
*天晴れ
いわゆる私は”おじいちゃん・おばあちゃん子”でした。
自営業で喫茶店を経営していた母に代わり、子供の頃は旅行などよく連れて行ってもらったものです。
私が小学生よりまだ小さかった頃、祖父は私を連れて飲み屋さんに行ったり(今の時代なら完全にアウト)、祖母には編み物を教えてもらったりと楽しい思い出がたくさん残っています。
祖母が亡くなって約30年。
先日、祖父が永眠いたしました。
特に大きな病気もなく天寿を全うした老衰で、90歳の大往生です。
私がこの仕事を始めようと思ったきっかけになったのが祖父の存在です。
ある程度の年齢になったら自分が死ぬ前のことと死んだあとのことを具体的に考え、家族や大切な人に自分の希望を伝えておくことで本人にとっても残される者にとっても後悔を減らすことができます。
私の場合は祖父が認知症になってから終活の重要性に気付いたので、祖父の希望を全て叶えられたかは分かりません。
「本人にとっていいようにしてくれること」と「家族がいいと思ってすること」は違うからです。
しかし、祖父が最期を過ごした施設では手厚いケアをしていただき、一人暮らしをしていた頃に比べて毎日が楽しかったと思います。
それは面会の時に見せる笑顔や、部屋に飾られていた季節行事の写真に写る満面の笑みを見れば分かります。
皆さんはどのような最期を迎えたいか、ぼんやりとでも考えていますか?
祖父が亡くなったことはもちろん悲しいですが、母も私も納得のお別れができました。
おじいちゃん、安らかにお眠りください。
-
*夏と高齢者
「暑いですね〜」
最近は人に会うたびに第一声がこれのような気がします(笑)
皆さん、いかがお過ごしですか?
梅雨明けが早すぎて、すっかり夏ですね。
暑さに老いも若きもないですが、やはり高齢者は特に気を付けないと夏バテしてしまうと思います。
筋肉量が減り、身体の機能が低下している高齢者は少しの油断が熱中症につながります。
以下のことに気を付けて生活していただきたいです。
- 暑い時間帯の外出は控える
- 出かける時は日傘や帽子、通気性の良い長袖の服を選ぶ
- 水分補給を忘れず、こまめに飲水する
- 室内の温度を調整する
高齢者の中には”もったいないから”とか”暑くないから”といった理由でエアコンや扇風機を使いたがらない人もいます。
でも、考えてみてください。
一番大切なのは自分の命です。
自分が快適に過ごせる環境を優先しなければ大変なことになります。
特に認知症になった場合、体温調節ができず、自分の着る服が選べない方もいます。
私の祖父がそうでした。
去年の夏、裏起毛のトレーナーに半纏を着て現れ、私をはじめ家族を驚かせました。
すぐに着替えてもらいましたが、背中は汗びっしょりで、でも本人は何とも思っていない様子。
高齢者は自分で気温や体調の変化に気付いていない場合もあるので、周りの人が気にかけてあげましょう。
当たり前のことですが、「食べること」「寝ること」「動くこと」は高齢者でなくとも生きていくうえで、とても大切なことです。
この夏を乗り切るために、普段の生活を見直し、生活のリズムを整えましょう。